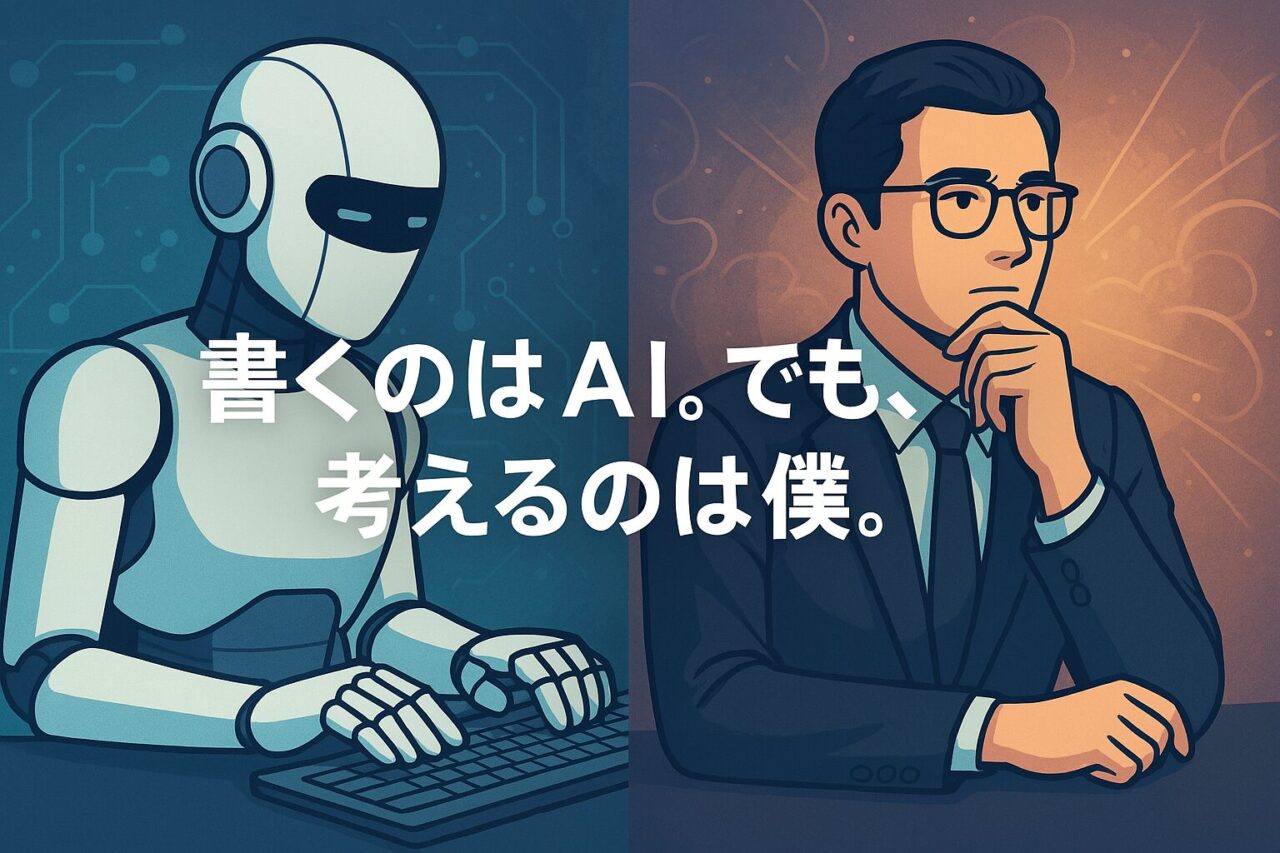こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!
最近は、名古屋・春日井エリアを中心に、企業や個人事業主の方から「AIって結局、何から始めたらいいんですか?」といった相談を受けることが増えてきました。
気づけば、コワーキングスペースの運営だけでなく、”AIを使った業務効率化の相談役”としての顔も増えてきています。
そんな僕が、ここ数か月毎日欠かさずやっているのが、ブログの更新です。実はこれ、AI(ChatGPT)を使いながら、構成・本文・SEO対策まで全部手を入れて書いているんですが──
「AIでブログ書いてるなら、サクッと書けるんでしょ?」よくそう言われます。でも、実際は1記事に1時間は当たり前、3時間かけることも普通にあるんです。
正直、30分で書こうと思えば余裕で書けます。15分だって可能です。でも、僕がこだわっているのは“コンテンツの質”です。
僕が届けたいのは、”誰でも知ってるような情報”じゃなくて、「なるほど、こうすればいいのか!」と膝を打ってもらえるような、実践的で一歩先をいく情報なんです。
そのためには、AIに頼るのではなく、AIと”対話しながら一緒に考える”プロセスが必要になります。でもその一方で、毎回毎回、構成を出させて、本文を書かせて、SEO要素を添えて──って、この”同じやり取り”にも結構時間を取られていたんですよね。
そこで導入したのが、ChatGPTのAPIを使った”下ごしらえの自動化”というアプローチ。今回の記事では、「魂を込めるために、まず”書かない”という選択をした僕」が、なぜChatGPT APIを使いはじめたのか、そしてそれが”手抜き”ではなく”質を上げるための戦略”である理由をお伝えしていきます。
AIに”書かせる”だけじゃ、僕の記事にはならない

僕のブログ記事は、ただChatGPTに「これで書いて」と投げて終わり、ではありません。もちろん、最初の骨組みをAIに出してもらうことはあります。
でもそこからが本番。構成を見て、「これじゃ弱いな」「こっちの順番のほうが読みやすいかも」と手直しして、さらに見出しごとに本文を細かく依頼しながらブラッシュアップしていきます。
ChatGPTは”考える相棒”であって、”自動ライター”ではない
たとえるなら、ChatGPTは優秀なインターンみたいな存在。こちらの意図をうまく伝えれば、それなりに良いものを出してくれるけど──そのままだと、”どこかで見たことあるような、ありきたりな記事”になってしまうことが多い。
僕が書きたいのは、そういう記事じゃない。読んだ人が「なるほど」「これやってみよう」と思えるような、”一歩先の役立つ情報”を届けたい。
そのためには、テーマに対して自分が本当に感じていることを深掘りしながら、ChatGPTとのやり取りを通して、思考を”言語化していくプロセス”が欠かせないんです。
だから僕は、記事を書いているというより、“考えながら言葉を彫っている”ような感覚でChatGPTと向き合っています。これが、1記事に1時間、時には3時間かかる理由です。
AIを使っているのに、時間が短縮されないどころか、むしろ深くなっていってるんです。でも、それは悪いことじゃない。なぜなら、ChatGPTをただの”自動ライター”ではなく、”思考の相棒”として使っているから。
このスタンスは今でも変わっていません。ただ、最近気づいたのは──「そのスタンスを守るために、もっと仕組み化できる部分があるんじゃないか?」ということでした。
「ありきたり」を超えるために、僕は”深掘る”
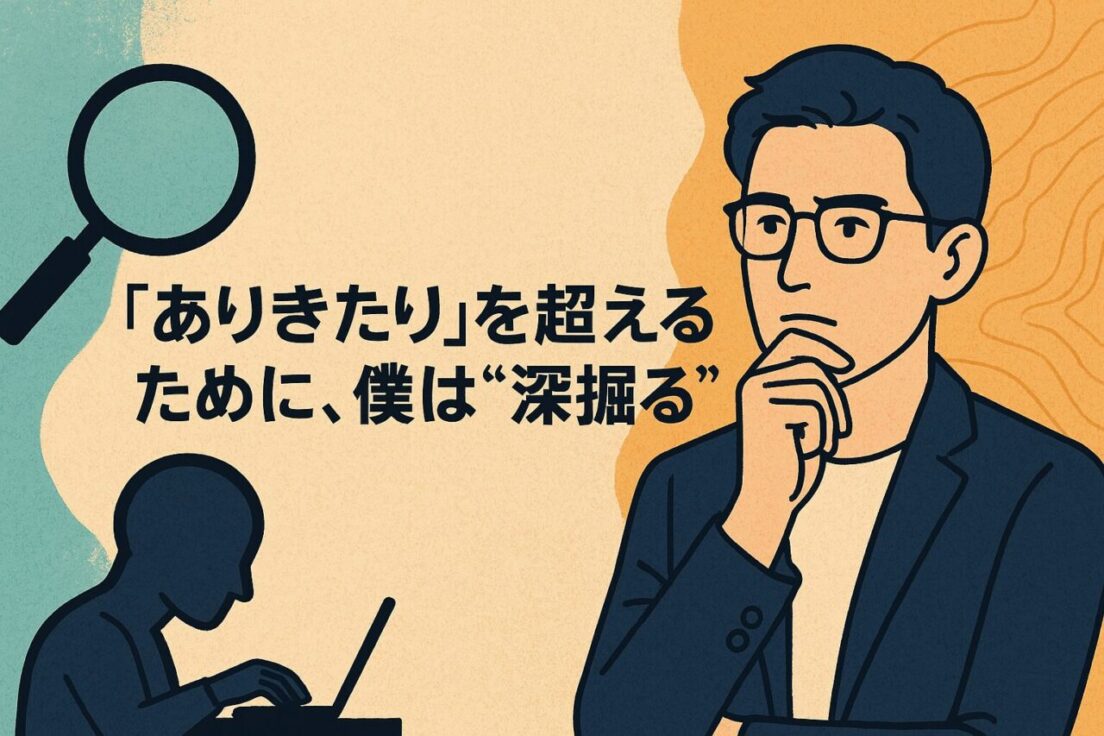
ChatGPTの表現力や文章のまとまり方って、正直すごいです。僕なんかより、ずっと読みやすくて、伝わりやすい。
……なんですけど、それでも出力された内容をそのまま出す気にはなれないんです。なぜか?
それは、どこかで読んだことがあるような”ありきたりな情報”になりがちだからです。もちろん、悪くはないんです。丁寧だし、無難で、破綻もしていない。
でも、読者の心を動かすのは”無難な情報”じゃなくて、”その人だからこそ書けた視点”なんですよね。
だから僕は、ChatGPTの出力を見ては、「これはちょっと深掘りが足りないな」と考え直し、「そう言えば先日こんな事例が実際にあったからそれ使おうよ!」「この視点から展開したら面白いんじゃないか?」と、毎回一歩、二歩と踏み込んだところにある”本質”を探しに行くようにしています。
これが、僕が”魂を込めて書く”って言ってる意味です。そしてこのやり方は、たとえAIがどれだけ賢くなっても、僕の中ではずっと変わらない。
でも、その”前段階”に時間かかりすぎ問題
とはいえ──その魂を込める前に、毎回同じやり取りを何度も繰り返してるのって、正直、非効率だなとも思ってたんです。
- 「このキーワードで構成出して」
- 「じゃあ、それぞれの見出しに本文つけて」
- 「タイトルはもう少しキャッチーに」
- 「SEO用のメタディスクリプションもお願い」
- 「アイキャッチ画像に使えそうなプロンプトも…」
この”毎回同じやり取り”だけで30分ぐらい取られることもある。しかも、これは僕がやりたい”深掘り”とは違う部分です。
だったら、この”前処理”だけでも仕組み化できれば、魂を込める部分にもっと集中できるんじゃないか?そう思ったのが、ChatGPT APIを導入したきっかけでした。
繰り返し作業はAPIに任せる:魂の前処理を自動化

じゃあ、僕がAPIで何をやっているのかというと──“記事を書くための前処理”を自動化しています。
具体的にはこんな流れです:
- スプレッドシートに「キーワード」を入れる
- ChatGPT APIでそのキーワードに合わせた「構成案」を生成
- その構成に沿って、「本文(セクションごとの下書き)」を生成
- SEO的に必要な「タイトル案」や「メタディスクリプション」も出す
- 最後に「アイキャッチ画像用のプロンプト」まで出力
この一連の流れを、1つのテンプレートで一括で出せるようにしたんです。そうすることで、毎回ChatGPTに同じことを聞かなくても済む。“いつものやり取り”を、仕組みの中にあらかじめ埋め込んでおくという感じです。
時間の節約以上に大きかった”集中力の温存”
もちろん、APIを使えば30分くらいかかっていた作業が数秒になります。でも正直、それ以上に大きかったのは──「どこまで人力でやるか?」を毎回判断するための”脳のエネルギー”を温存できるようになったことです。
- 「今日はこの構成でいいかな?」
- 「メタディスクリプション考えるの、今やるべきかな?」
- 「見出しに数字入れた方がいいんだっけ?」
──こういう細かい判断の積み重ねって、案外エネルギーを食うんですよね。APIでそこをまるっと処理しておくことで、“今どこに注力すべきか”がクリアになる。
だから、僕が本当に時間をかけたい「伝えたい中身」や「読み手の気持ちを想像する時間」に集中できるようになりました。
書くことは減らない。でも”悩む時間”は確実に減った
誤解してほしくないのは、APIを使っても僕の執筆スタイルが楽になったわけじゃないということです。むしろ、もっと深掘れるようになったから、記事は前より長くなってるし、時間もかかってます(笑)
例えばAIを使ってブログを書き始めた頃の文字数は2500文字ぐらい。
この時は、十分書けていたと思ってたけど、深掘りすればするほど文字数は増え今日の記事はざっと4000文字ぐらい。少ない日でこれぐらい書きます。
大体8000文字ぐらい
多いときは13000文字ぐらい書きます。
でも、不思議と疲れ方が違う。文章を整えるとか、SEO要素を入れるとか、そういう”作業系の悩み”が減ったことで、純粋に「考えること」にエネルギーを使えるようになった感覚があるんです。
これは、文章に魂を込めたい人ほど、きっと実感できるはずです。
まとめ:手を抜かずに、手順を抜く。それが”魂を込める自動化”

AIを使う=手抜き、というイメージを持たれることもあります。でも実際はその逆で、僕はAIを使うことで、もっと深く考えるようになりました。
毎回の繰り返し作業をChatGPT APIに任せたことで、”記事を量産するため”ではなく、“一記事一記事をもっと丁寧に書くため”の余白が生まれたんです。
もちろん、僕のように毎日AIとやり取りしてブログを書くスタイルは、万人に合う方法じゃないかもしれません。でも、AIと一緒に深く考えたい人、質にこだわって書き続けたい人には、APIを使った仕組み化はめちゃくちゃ相性がいいと感じています。
もし、「AIは使ってるけど、なんか浅くなってきたな」とか、「記事を書く体力がもたない…」と感じているなら、”書く”ことより先に、”整える”ことを自動化してみると世界が変わるかもしれません。
そして、実際に僕がどんなふうにAPIを使っているか、そのテンプレやコードはnoteで公開しています👇
👉 ChatGPT APIで”1日1記事”を自動生成する方法【テンプレ付き】- 近日公開
※Room8ブログでは全体像を、noteでは実装とテンプレを紹介中です。
「魂を込める」のはAIじゃなくて、自分です。でもそのために、AIに手伝ってもらえることは、どんどん任せていく。僕はこれからも、そんな”余白の作り方”をアップデートし続けたいと思っています。