こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!
最近は、名古屋・春日井エリアを中心に、企業や個人事業主の方から「AIって結局、何から始めたらいいんですか?」という相談をいただくことが増えてきました。
ChatGPTや生成AIを“なんとなく便利そう”と思っていても、いざ業務に取り入れようとすると、何をどう活用すればいいのかで手が止まってしまう……。そういう声、めちゃくちゃ多いです。
僕自身も、はじめは「AIってつまり答えてくれる便利な検索窓でしょ?」という認識だったんですが、
ここ最近の進化っぷりを見ていると、どうやら話はそんなに単純じゃないぞ、と。
特に注目したいのが、AIが「質問に答える存在」から、「自分で動いて、仕事を進める存在」に進化してきているという点です。
ちょっと前まで夢物語だった「AIがAIと話し合いながらプロジェクトを進めてくれる」みたいな話が、
いま本当に動き始めています。
ということで今回は、“AIがチームで仕事をする時代”に入ってきた今、
僕たちが知っておきたい考え方や、実際にどう活用できるのか?について、わかりやすくお伝えしていきます。
AIが“チームで動く”時代へ:個人の活用から自律型エージェントへ
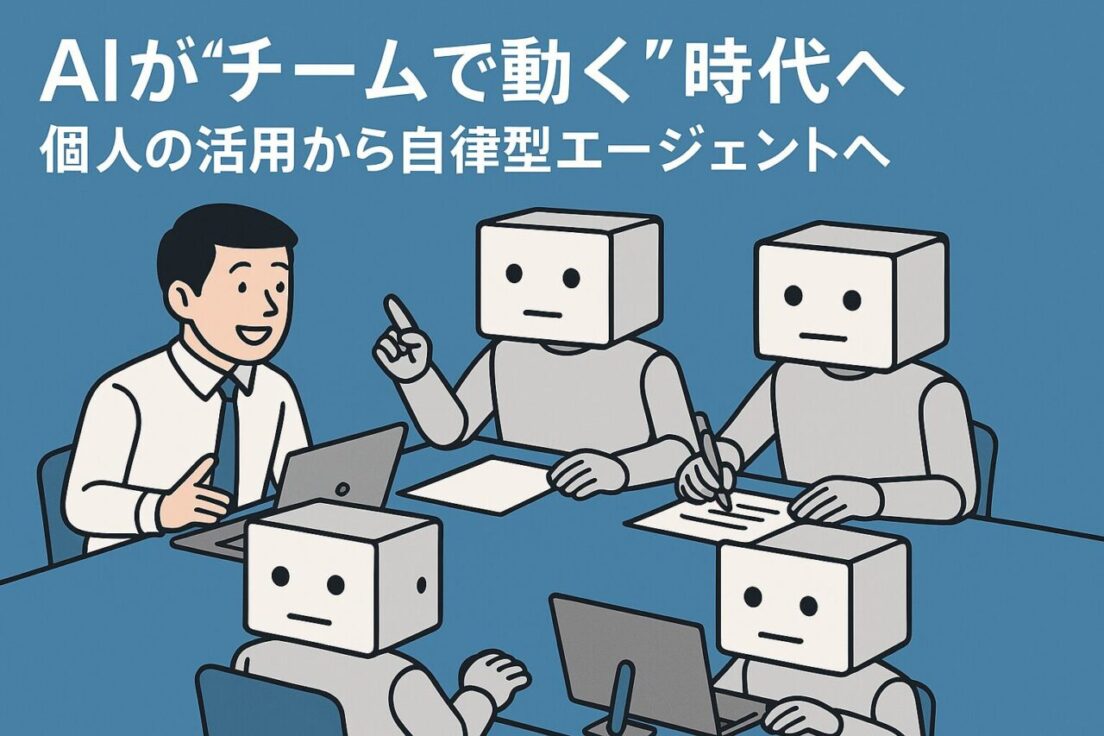
ChatGPTを使って「文章作成」や「要約」などの作業を自動化する人は増えましたが、それはあくまで“1つの作業をAIが手伝ってくれる”という範囲にとどまっています。
ここまでは、いわばAI=1人の助手という使い方。
でも、最近の進化はその次のステージに入っています。
それが「AIが複数連携して、自律的にタスクをこなす仕組み」です。
つまり、人間が細かく指示を出さなくても、AI同士が役割分担をしながら
「企画→実行→フィードバック」までを自動的に回す“チーム”として働いてくれる世界観。
この構造は「マルチエージェントシステム」や「AIエージェント」などと呼ばれ、AutoGPTやLangGraph、CrewAIといった海外のプロジェクトが火付け役になっています。
たとえば、あるエージェントが「ブログ記事のテーマを決める」役割、別のエージェントが「本文を書く」担当、さらに別のエージェントが「SEOの最適化や投稿作業」を受け持つ——
そんなふうに、一つのゴールに向かってAIたちが役割分担しながら自律的に動くという設計です。
ここでポイントなのは、AIが「1回1回プロンプトで指示される存在」ではなく、目標さえ与えれば、自分たちで考え、作業を進め、必要なら相談までするという点。
そして実は、これらの仕組みはすでに個人でも試せる段階にあります。
技術的な知識があまりなくても、FlowiseやRework.aiといったノーコードツールを使えば、簡単なワークフロー型エージェントを自作することも可能です。
つまり、個人や中小企業でも「自分の中にミニチームを持つ」という感覚が、現実的になってきている。
この変化は、単なる“作業効率”にとどまらず、「働き方の再設計」や「組織構造の最適化」といった、本質的な変化につながっていく可能性があります。
かつては、チームを持つには人を雇うしかなかった。
でもこれからは、AIに“職能”を持たせ、チームを設計していくことそのものがスキルになっていく。
そう考えると、このAIエージェントの流れは、単なる流行ではなく「働くこと」の定義そのものを変える分岐点になるかもしれません。
「AIにお願いする」から「AIが相談してくる」時代へ
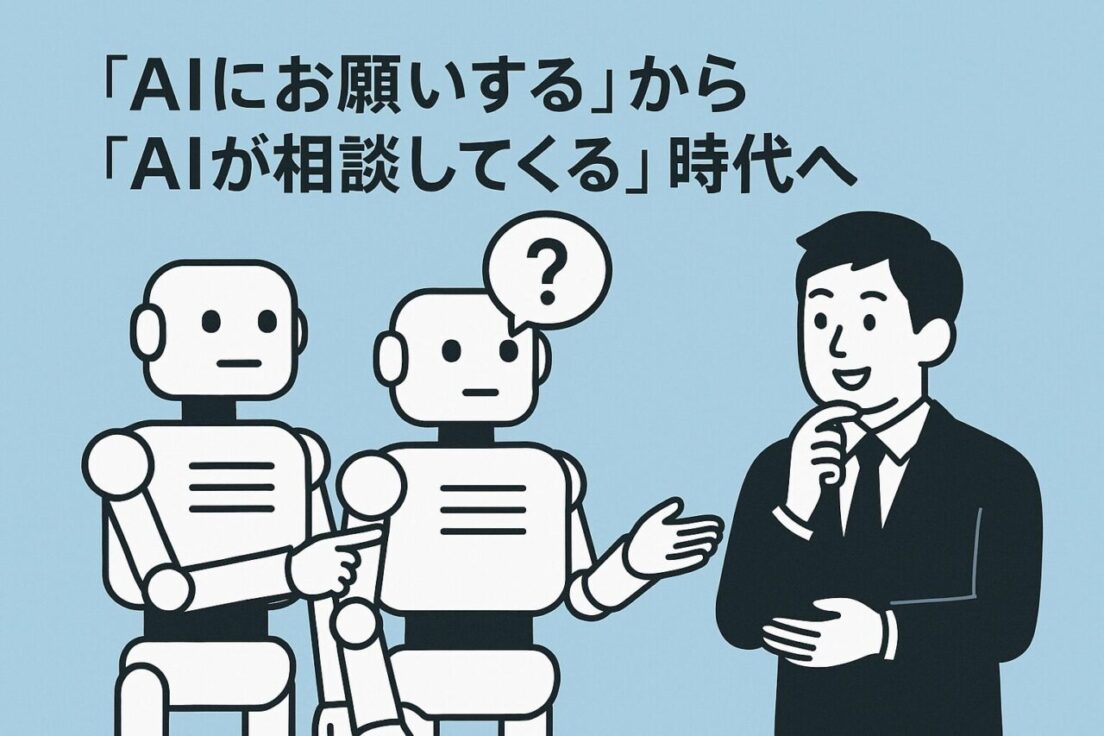
これまでのAIの使い方って、「〇〇をやって」とか「この文章を要約して」みたいに、
こちらから指示を出して、それにAIが反応する“呼びかけ型”の関係性が基本でした。
でも、AIエージェントがチームで動くようになると、この関係性がじわじわと変わってきます。
たとえば、あるAIに「3日以内にSNS用の販促キャンペーンを企画して」と頼んだとします。
すると、昔のAIなら「了解です!」って勢いで(たぶん何も分かってないまま)やり始めて、
“なんとなくそれっぽいけど、全然ズレてる企画”を出してきたりしました。
いわゆる“幻覚を生むAI”の典型パターンですね。
僕自身も、これまでに何度も「いや、分からなかったら聞いてよ!!」って思ったことがあります。
確認せずに勝手に創作する姿勢に、正直イラっとした経験がある方も多いんじゃないでしょうか。
でも最近のAI、特にエージェント型のものは、そこが大きく変わっています。
「これって、キャンペーンのターゲット層はどのあたりですか?」
「インスタとX、どちらをメインにしますか?」
「過去の投稿で反応がよかったものはありますか?」
みたいに、“足りない情報はちゃんと聞いてくる”ようになったんです。
つまり、指示を“ただ処理する存在”から、“状況を理解しようとする存在”へと進化してきた。
これは技術的には、AutogenやLangGraphのようなエージェントフレームワークによって、
「AI同士が対話しながら判断する構造」が組めるようになったからです。
しかも面白いのが、彼らは勝手にこっちに相談してきたり、Slack風のUIで
「これって本当に今週の優先事項ですかね?」みたいなコメントをしてくることもある。
そう、AIが“必要な情報を取りにくる”=相談するAIになりつつあるんです。
この変化は、単に便利なだけでなく、“一緒に働く感覚”を強くしてくれる側面もあります。
今までは「お願いする → 結果が返ってくる」という一方通行だったのが、
これからは「目標を共有して、一緒に最適解を探す」みたいな、コラボレーション的な関係に近づいていく。
AIは、もう“道具”じゃなくて、“対話するチームメンバー”。
この感覚がピンと来るようになると、AIとの付き合い方がガラッと変わってきます。
「とりあえず一人雇うなら、AIでもよくない?」って思ってきた人へ
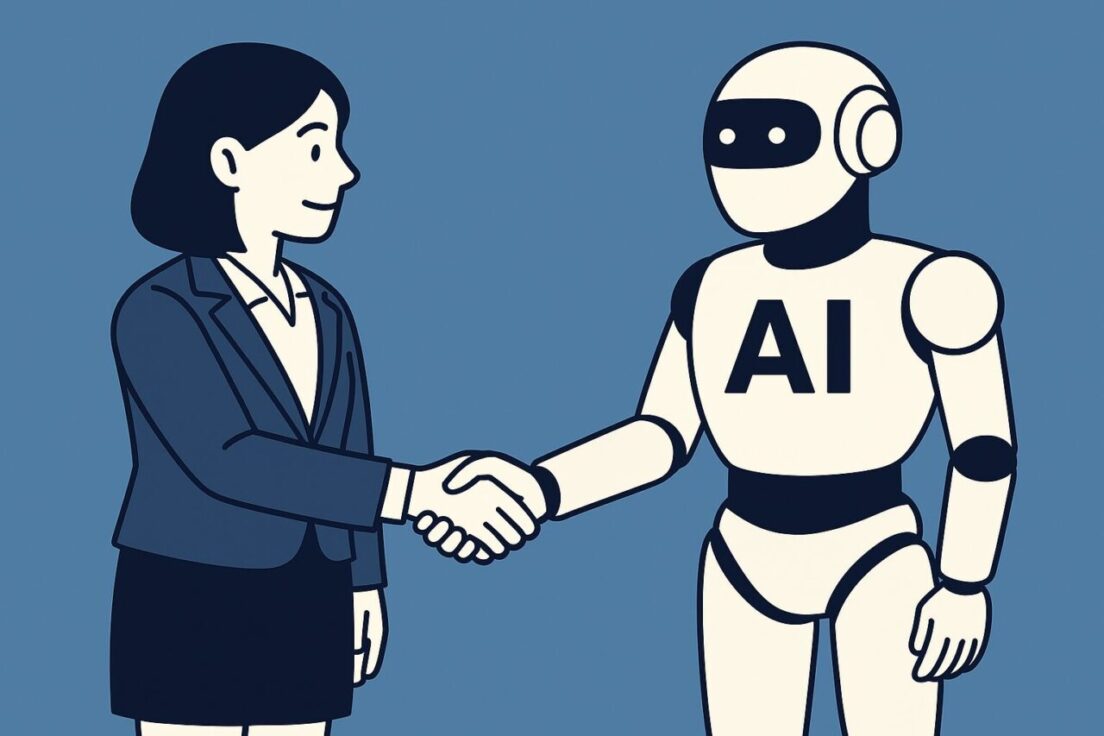
中小企業や個人事業主の現場って、「やることは多いけど、人を増やすのは難しい」というジレンマがずっとあります。
求人を出してもなかなか集まらないし、ようやく採用できたとしても、
教育や定着にコストも時間もかかる……。それでも仕事は待ってくれない。
僕も春日井でコワーキングスペースを運営しつつ、企業さんのAI導入支援をしている中で、
「人が足りない。でも雇うほどじゃない。でも回らない」という話を何度も聞いてきました。
そんなときに浮かんでくるのが、「これ、AIで代替できないかな?」という問いです。
もちろん、AIは“人間の代わり”じゃない。
でも、「人を雇うには少し早い」というグレーゾーンには、むしろAIがフィットすることがあるんです。
たとえば、
- 営業のリスト作成を毎週お願いしたい
- SNSの投稿を考えて、毎週スケジュール化したい
- ブログ記事の構成とタイトルを仮で出しておいてほしい
- メールの返信文面を一旦案として出しておきたい
……こういった業務は、「指示があれば人じゃなくてもこなせる」タイプのタスク。
まさにAIの得意分野です。
ここで面白いのが、一人のスーパースタッフを探すよりも、「3人のAIを連携させた方が効率的」ってケースが出てきていること。
たとえば:
- ChatGPTで文章の草案を作る
- 画像生成AIでバナーを作る
- タスク管理ツールとZapierで自動投稿を組み合わせる
こういった流れを仕組みとして作ることで、“ちょっとした業務”が自動で回り始める。
しかも、ミスしても文句も言わないし、土日も稼働できる。すごい。人間としては嫌だけど、ビジネスとしてはありがたい。
もちろん「全部AIに任せて安心」なんて話ではありません。
でも、「一部の繰り返し作業を任せて、自分は判断に集中する」というスタイルにすることで、
中小企業でも“小さな余裕”が生まれるのは事実です。
“今すぐ社員を一人雇う”という選択の前に、
“AIを一人チームメンバーとして迎え入れてみる”というのも、これからの選択肢のひとつになるはずです。
じゃあ“そのAIチーム”ってどう作るの?
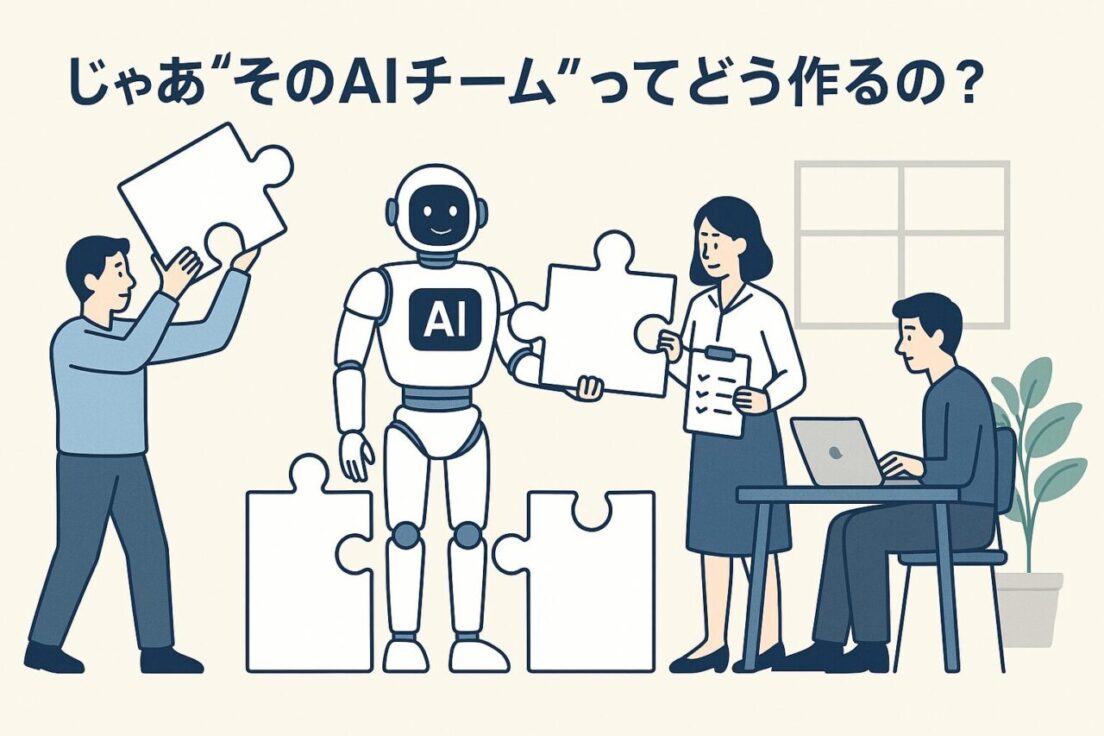
ここまで読んで、「そんなこと言われても、AIをチームで動かすってどうやんの?」って思った方。
はい、正しい反応です。“すごそうな話”と“自分でやれる話”の間には、でっかい川があります。
でも安心してください。
今はこの川、想像以上に“浅い”です。
ちゃんと道具と手順を選べば、専門知識がなくても“小さなAIチーム”を作ることは十分に可能なんです。
まずは「役割を分ける」ところから
いきなり「LangGraphでエージェント構築!」みたいなガチ開発を目指す必要はありません。
むしろ最初は、“頭の中にいる3人”をAIとして分けて考えてみるところからスタートしましょう。
たとえば、あなたがブログ記事を書くなら:
- 👨💼 企画担当:「どんな内容がいいかな?構成はどうする?」
- ✍️ ライター:「じゃあ本文書いてみますね」
- 🕵️♀️ 校正・確認:「この表現、分かりづらくない?直しておきます」
この3人、それぞれ別の役割を持ってるはずです。
これをChatGPTや他のツールに“個別に”指示を出す設計に変えていくのが第一歩。
ツールを組み合わせて“動き”を生む
ここで使えるのが以下のようなツールたち:
- ChatGPT / Claude / Gemini:テキスト処理、文章生成のメイン役
- Zapier / Make(旧Integromat):ツール同士の連携、自動化フローの構築
- Notion / Google Sheets:情報の整理や一時保管に
- Flowise / Rework.ai:ノーコードでエージェント型ワークフローを構築できるUIツール
これらを使えば、たとえば「ブログのネタ出しをしたら、それが自動で構成案になり、下書きが生成されて、カレンダーに登録される」といった、“人がひとつずつ操作しなくても勝手に進む”フローを作れます。
難しいのは「技術」じゃなくて「設計」
そして多くの人がハマるのが、「AIが使えない」ではなく、
「何をどう任せて、どこで人間が関わるかを設計していない」という問題。
ここでポイントになるのが、“目的から逆算して役割を決める”という考え方。
✏️目的:週1でブログを出したい
→ 役割分担:企画(AI)→構成(AI)→草案(AI)→編集(人)→投稿(AI+人)
こうやって“チームっぽい流れ”を想像するだけで、一気にやるべき設計が見えてきます。
小さく試して、徐々に“自分だけのAIチーム”を育てよう
最初から完璧に組む必要はありません。
むしろ「ちょっとAIに役割を分けて任せてみた」くらいがベストなスタート。
一度動き始めれば、毎回指示を出す面倒さからも解放されていきます。
気づいたら、「あれ、これ人だったら月5万くらい払ってたな……」ってくらい働いてくれてたりします(笑)
このあたりの流れは、今後noteの方でもテンプレート付きで具体事例を公開する予定なので、
「興味あるけど、どう始めていいか分からない」という方は、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。
まとめ:AIは“道具”じゃなく、“仲間”になっていく
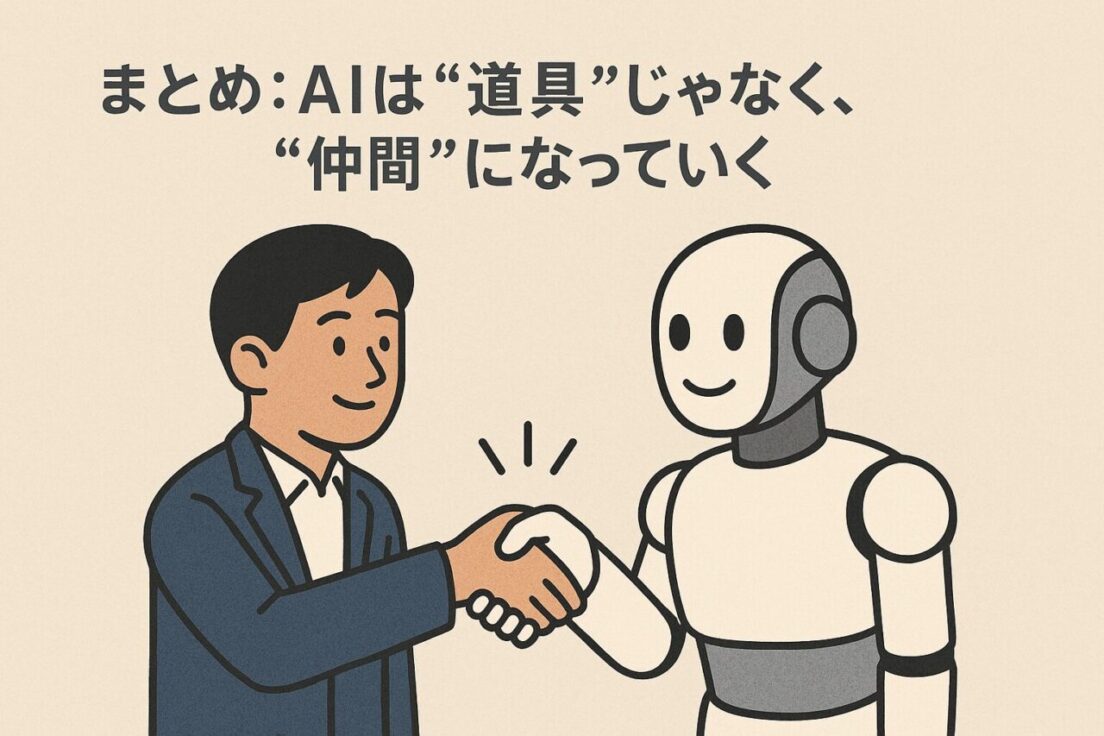
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
「AIが仕事をする」なんて言うと、なんだか遠い未来の話に聞こえますが、
実際には、“少しの工夫”と“少しの設計”で、今日からでも始められる働き方の進化です。
特に中小企業や個人事業主にとって、
「雇うにはまだ早い。でも誰かの手がほしい」
そんな“隙間”にフィットするのが、今のAIの立ち位置だと僕は思っています。
大切なのは、「どのAIを使うか」よりも、
「どういう流れで仕事が進むと、自分がラクになるか」を見つめること。
そして、その流れに少しずつAIを組み込んでいくことで、
あなたの中に“もうひとつのチーム”が生まれていく。
Room8では、こうした「AIと一緒に働く仕組み」の設計や導入のご相談も受け付けています。
「AI使ってみたいけど、何からやればいいの?」という方は、ぜひお気軽に声をかけてくださいね。
→ Room8公式サイトはこちら
→ noteでは導入事例やテンプレも公開中
AIに仕事を奪われるんじゃない。
AIに、面倒な仕事を任せて、自分にしかできないことに集中する。
そんな未来を、一緒に作っていきましょう。

